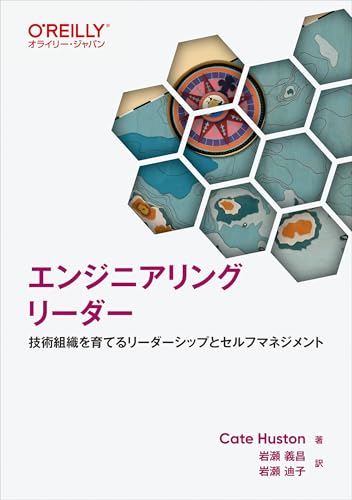エンジニアリングリーダーは何を考えて・日々どんな葛藤があって・どんな挑戦をしているんだろう?そんなエンジニアリングリーダーの具体的かつ実践的なプラクティスやマインドセットがまとまった一冊「エンジニアリングリーダー ―技術組織を育てるリーダーシップとセルフマネジメント」を読んだ📕
僕自身のリーダーシップ経験を振り返りながら読むことができて,答え合わせにもなったし,新たな発見もあって良い本だった💡
2025年10月28日に出版された新著で本書は翻訳を担当された @iwashi86 さんに送っていただいた❗️
出版おめでとうございます🎉 いつもありがとうございます〜
10月28日に出版される「エンジニアリングリーダー ―技術組織を育てるリーダーシップとセルフマネジメント」を翻訳された iwashi-san に送っていただきました📕出版おめでとうございます🎉これは読むの楽しみすぎる❗ブログも書くぞ〜 pic.twitter.com/V1j4E6tfaM
— カック (@kakakakakku) 2025年10月19日
目次
- 第I部 あなた自身について
- 第1編 自分自身のキャリアの DRI になる
- 1章 キャリアの決定と最適化
- 2章 キャリアの目標を設定し、実践する
- 3章 成長を積極的に受け入れる
- 4章 前進する
- 第2編 セルフマネジメント
- 5章 エネルギー管理
- 6章 マネージャーの仕事の定義と適応
- 7章 リーダーとしての幅を広げる
- 第1編 自分自身のキャリアの DRI になる
- 第II部 チーム
- 第3編 チームのスケーリング
- 8章 スケールする採用
- 9章 みんなを成功させる
- 10章 ベンチの構築(次世代リーダーの育成)
- 第4編 自己改善するチーム
- 11章 ミッションと戦略
- 12章 戦術と実行
- 13章 改善の推進
- 第3編 チームのスケーリング
- 第III部 結論
- 14章 「良い状態」とはどういうことか
どの章も良かったけど(マーカーをたくさん引いた🎨)個人的に特に良かった3つを選ぶなら以下かな❗️
- 3章 成長を積極的に受け入れる
- 10章 ベンチの構築(次世代リーダーの育成)
- 14章 「良い状態」とはどういうことか
僕自身のリーダーシップ経験
本書の感想をまとめる前に僕自身のリーダーシップ経験を簡単にまとめておこうと思う.責任範囲は小さめだとは思うけど SIer 時代のチームリード・スタートアップでのテックリードとエンジニアリングマネージャなどを経験している.
また2023年4月からはフリーで活動していて,ソフトウェアエンジニアリング全般の支援をしつつ,テックリード育成や次期テックリード候補の育成もしている.本書で言うと 10章 ベンチの構築(次世代リーダーの育成) の内容がまさに❗️という感じだった.
リーダーシップ関連のアウトプットだと以下などは過去にまとめたことがある🔗(2017年〜2018年の話だけど!)
読者層
もしかしたら本書のタイトルを見て「リーダーが読む本でしょ?自分はリーダーじゃないし読者層じゃなさそう...」って感じる人がいるかもしれないなと思った😀逆にそういう人にこそ読んでもらいたく「誰もがリーダー」というマインドセットを獲得できそう.ちなみに本書の冒頭にも以下のように書いてあって,IC (Individual Contributor) にも読んで欲しいと書いてあるよ \( 'ω')/
本書は、主に2種類の読者を想定しています。まず、エンジニアリングチームを率いるリーダーです。そして、コードを書く、プロダクトをリリースするといった日々の業務を担う IC です。

コーチャブル
「自分自身のキャリアの DRI になる」という話が本書の冒頭(第1編)に出てくるのが著者の狙いなのかな?と感じた.DRI (Directly Responsible Individuals) を自分自身のキャリアに当てはめるという視点はすごく良くて,リーダーは自己犠牲を前提にせず,自分自身のキャリアの主導権をちゃんと握るべきという "ある意味当たり前" の内容で共感できた.
特に 3章 成長を積極的に受け入れる では「コーチャブル(アドバイスを受け入れられる状態のこと)」という話が出てきて印象に残った.エンジニアリングリーダーに限った話ではないけど,コーチャブルであるためにはどういうマインドセットを持っておくべきなのか?という解説があって自分自身を振り返るきっかけにもなった😀
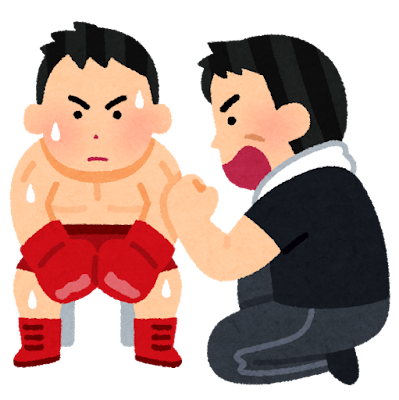
また 4章 前進する の最後に「自分自身のキャリアの DRI になるためのアクションプラン」が載っていた.僕自身はかれこれ10年ほど「1週間を振り返る」という活動を習慣化していて,紙に仕事の感想やキャリアへの期待・違和感などを自由に書き出している(見せられるものではないけど!).そのときにアクションプランの 1,2,4,6 を書くこともあって,僕自身の活動の答え合わせになった❗️
- 転職すべき時か評価する
- キャリアの選択肢として何を手に入れたいか検討する
- 雇用主と交わした条件を明確にする
- 近い目標を特定する
- フィードバックへの向き合い方を考える
- あなたの人脈を確認する
リーダー育成
僕自身のリーダーシップ経験 にも書いた通り,仕事でリーダー育成を支援する機会がある.また技術講師として人材育成に携わった経験も長く 10章 ベンチの構築(次世代リーダーの育成) を読みながらリーダー育成もエンジニアリングリーダーの仕事だよなぁ〜と改めて感じた.ちなみにマネージャから次期テックリード候補としてメンバーを紹介されることもあるし,本書にも書いてある「潜在能力の見極め」をしながら将来を任せられそうな人を探すこともある.
そして 10章 ベンチの構築(次世代リーダーの育成) には「ストレッチアサインメント」という話もあって良かった.客観的にコンフォートゾーンから少し離れる課題解決を見極めてリーダー候補に挑戦してみる?と提案したりすることがある.とは言え無責任に任せることはせず,成功するためのあらゆる支援はするし,Fearless Change を読んでもらったりもする.内容的には 9章 みんなを成功させる にも関連してる😀
ストレッチアサインメントの話で1つ刺さったのは「成長の機会」と「お願い」は違うということ.ちゃんと「成長の機会」になるような課題解決を見極めることが重要なのは改めて気を付けよう❗️
良いチームとは
最後の章だけど 14章 「良い状態」とはどういうことか の冒頭に以下の文章があって印象に残ったのと同時に「それな❗️」という気持ちになった.皆さんには ずっと記憶に残るようなチーム ってあるでしょうか?僕自身には大きく2つあって,今でもそのチームでの成功体験を再現できないか考えることもあるし,そのチームで久し振りに集まると必ずその当時の話題になったりもする💪
良いチームとは、人を変えるチームです。その人自身がより自分らしく参加できるチームであり、その人は次に働く場所でも良い環境を期待するようになります。良いチームは、あのチームで働いたことは忘れないと、キャリアの中でずっと記憶に残るようなチームです。良いチームは当然のことながらビジネスでの成果を出し、学びと成長を実現するチームです。なぜならそれが、メンバーが望むチーム運営方法だからです。
もしかしたら最初にザッと 14章 「良い状態」とはどういうことか に目を通して,"こういう良い状態" を作るためにはどういうプラクティスやマインドセットが必要なんだろう?と逆算しながら 第II部 チーム を読み進める流れが効果的かもしれないなぁ〜と思ったりした \( 'ω')/
その他読書メモ
訳注の親切さはさすがすぎた👏 正直 ブログラマ は一瞬誤植かと思ったw あと外資系企業にいるとよく聞く気がするけど スキップマネージャー(ドッテッドマネージャーもいたりする) や PIP や IC (Individual Contributor) などはちゃんと訳注が入っていて助かる人が多そう.
本書の中で「GIVE & TAKE」という本が引用されてて,読んだことがなかったから気になる.
マネージングアップの重要性という話も出てきて,横道さんの資料を思い出したりした💡 speakerdeck.com
13章 改善の推進 でボトルネックを解消したらチーム全体の処理能力が上がるという話があって,ザ・ゴール(制約理論)の話が来るか〜?と思ったら来なくて別の本が紹介されていた😀
誤植
- P191
と呼ぶもの取り組んでいる企業→と呼ぶものに取り組んでいる企業 - P.377
メンバーが望むのチーム運営方法→メンバーが望むチーム運営方法
まとめ
「エンジニアリングリーダー ―技術組織を育てるリーダーシップとセルフマネジメント」とても良かった📕
定期的に読み直す一冊❗️改めて出版おめでとうございます🎉